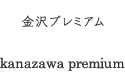おそろしい小説だ。
社会的に「正しくない」と告発された作家は施設に軟禁され、表現の自由も奪われる。
読み出してそう遅くないうちに、主人公と私たち読者は気づく。外からの助けは絶望的だと。
その施設の存在は世間には知られることなく、当人たちだけを残して日常は何の変化もなく続いていくのだろう。
そうしていつの間にか自分たちの思想がコントロールされていることに気付いたときにはすでに後戻りができないところまできているのだ。
その先の未来はどうなるのか、過去の歴史を知る読者なら想像は簡単だ。
その輪郭のない巨大な力に抗う術はあるのだろうか。
この小説の唯一の救いはフィクションであるということだ。
ただ、現実とこの小説世界の距離はどれだけ離れているのだろう。
ラストの主人公の姿が頭から離れない。